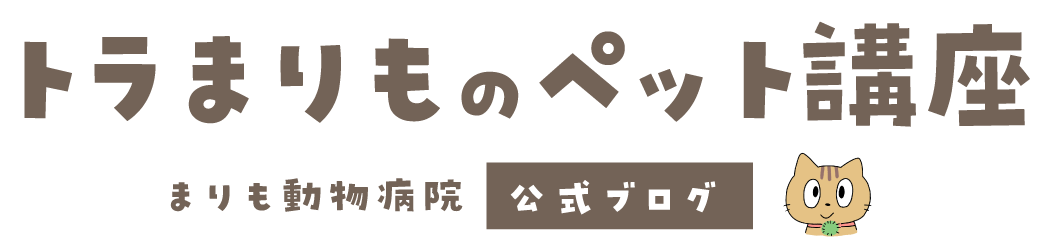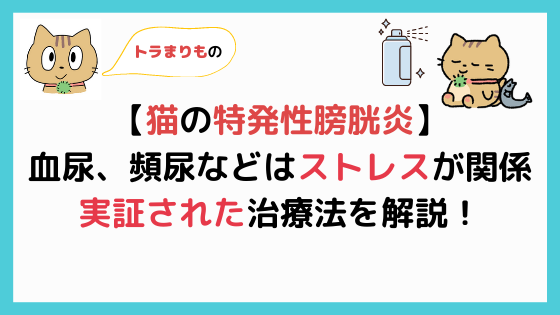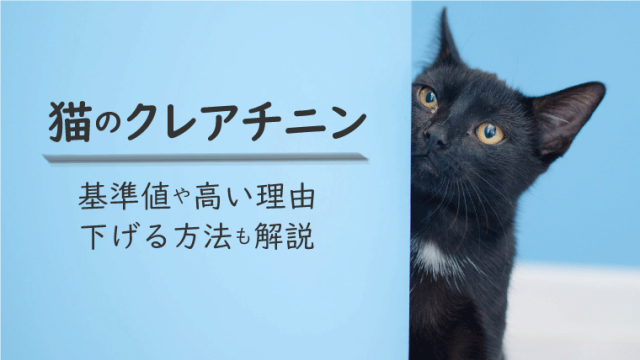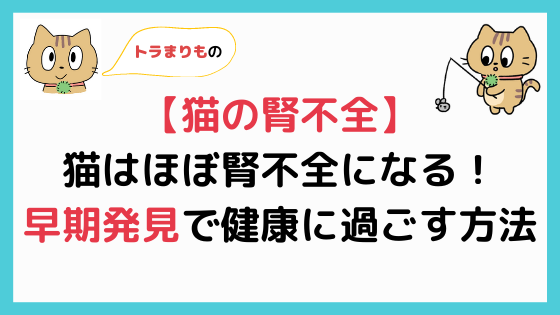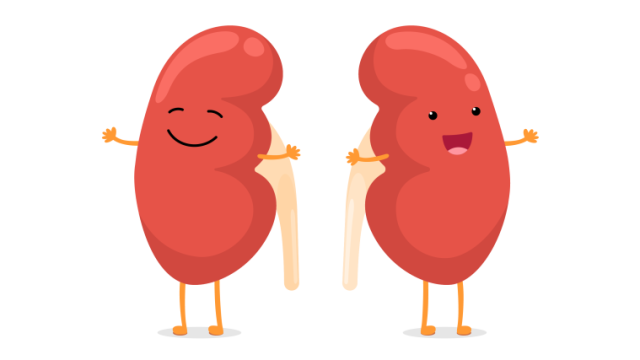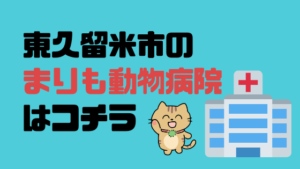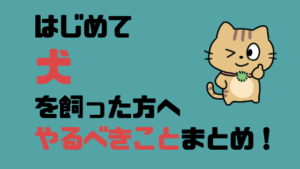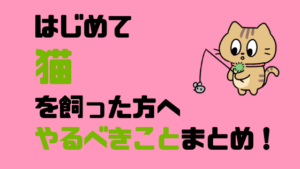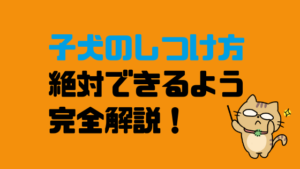「愛猫がなんどもトイレに行きます…」
「数日間、おしっこをしていない気がします…」
こんなときは、猫の尿道閉塞(にょうどうへいそく)の可能性があります。
尿道閉塞は緊急疾患であり、早く処置をしないと亡くなることもあります。
この記事では、猫の尿道閉塞について、
- どんな病気なのか?原因は?
- 症状や治療法(手術)は?
- 予防するには?
などを、獣医師が分かりやすく解説いたします。
「愛猫が尿道閉塞と診断されました…」「尿道閉塞はどんな病気なの?」という飼い主様は、ぜひ読んでみてくださいね。
猫の尿道閉塞は突然やってくる病気~原因とは?

猫の尿道閉塞は、ある日突然やってきます。
尿道閉塞とは、石(尿路結石)や炎症で生じる物質などにより、尿道がつまって尿が出せなくなる病気です。
- 尿路結石(ストルバイト、シュウ酸カルシウムなど)
- 炎症産物(炎症にともなって生じる物質)
- 血餅(けっぺい;血のかたまり)
- 腫瘍
- 外傷
- 尿道栓子(にょうどうせんし;尿道からはがれた細胞)
また、特発性膀胱炎などの基礎疾患があり、生じることもあります。
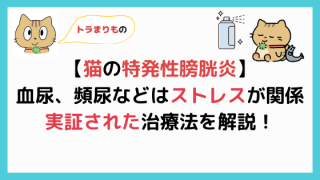
猫の尿道閉塞は、尿道がせまいオス猫での発生が非常に多いです。
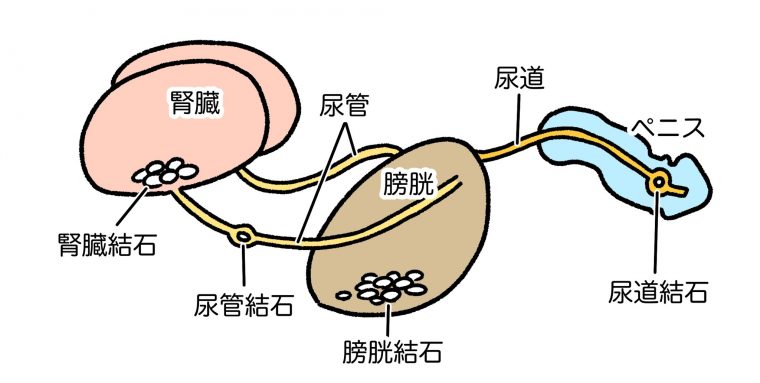
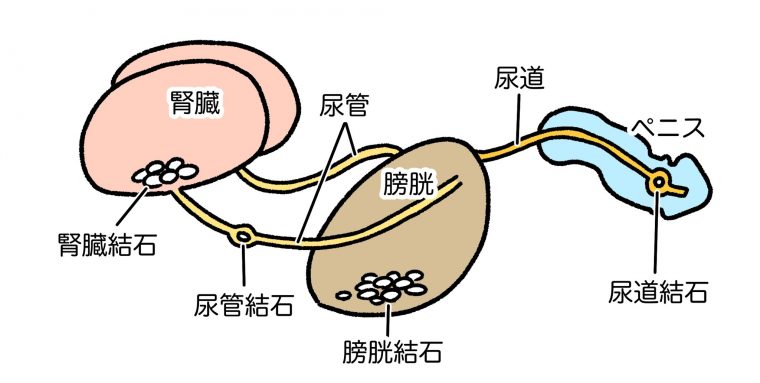
なぜなら、メス猫の尿道は太く直線的であるのに対し、オス猫の尿道は細くかつS字状に湾曲しているためです。
特に、水をあまり飲まなくなる寒い時期に多発します。
はやく対処をしないと、尿毒症によって亡くなってしまうこともあります。
猫の尿道閉塞の症状は『なんどもトイレに行くのに出ない』


猫の尿道閉塞の症状で最も多いのは、『なんどもトイレに行くのに出ない』です。
尿道がつまっているため、おしっこが出せません。
その結果、膀胱がパンパンになってしまい、より強い尿意を感じるけど出ない…
という状態です。
いよいよ膀胱のおしっこが満タンとなり、尿毒症になってしまった場合には、
- 食欲不振
- 嘔吐や下痢
- ぐったり
- けいれん
といった症状もみられます。
こうなると、様子を見ている時間はありません。いち早く動物病院へ!!!
ただし、猫がなんもトイレに行くときは、『膀胱炎』が原因であることも多いです。
膀胱炎の場合は緊急性が低いことがほとんどです。
見極めは難しいですが、メス猫であり、元気や食欲があって、毎回数滴(1円玉程度)が出ているようであれば、膀胱炎であることが多いです。



猫の尿道閉塞の治療は、すぐに開通させること~動物病院へ急げ!


上記のような症状がみられた場合は、特にオス猫であるなら、すぐに動物病院に行きましょう。
もし主治医の先生がお休みならば、別の動物病院や救急病院・夜間病院に行きましょう。
処置は尿道からカテーテルを挿入して、おしっこを出させるようにします。
つまりが強い場合には、生理食塩水を入れる、かたいカテーテルを用いるなどして対応します。
カテーテルが挿入できない場合には、ひとまずの処置として、膀胱に細い針を刺しておしっこを抜いて対処します。
(ただ、パンパンに膨らんだ風船に針を刺すことと同じですので、破裂をしてしまう可能性もあります。)
うまくつまりを解除できたら、尿道カテーテルを入れたまま、
- 膀胱洗浄(石や炎症物質を洗い流す)
- 点滴処置(血液バランスを整える+尿路をきれいにする)
などの処置を行い、退院します。
入院するか、通院になるかは、症状や血液検査の結果、つまりの度合いなどで判断します。
猫の尿道閉塞は、再発も多く、「退院できたのにまた入院…」といったこともよくあります。
猫の尿道閉塞~3つの内科療法


猫の尿道閉塞は、つまりの解除ができたら終了!というわけではなく、再発予防の治療が必要です。
①食事療法
猫の尿道閉塞に対して、食事療法はとても重要です!
結石が原因で尿道閉塞になることが多いので、結石の種類に応じた療法食を食べさせるようにしましょう。
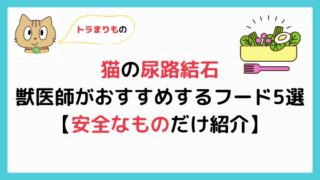
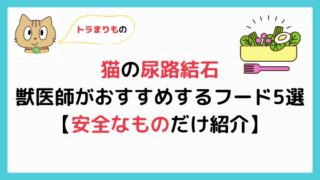
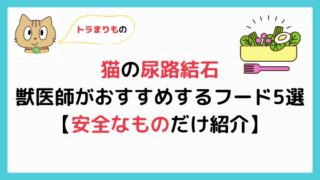
ちなみに、よく様々な療法食を混ぜてあげている方がいらっしゃいますが、基本的には混ぜたらNGです。
ただ、療法食を食べないことは、とっても多いです。
そのため、「なかなか食事を摂ってくれません…」という場合には、以下の記事をご参照ください。▼



②飲水させる
水を飲むことで、石のもととなる結晶や炎症で生じた物質などを、おしっことして排せつさせます。
ただ、愛猫に「水を飲んで!」と言っても、なかなか飲んではくれないですよね…
猫の祖先は砂漠に住む動物ですので、水をあまり飲みません。
現代を生きる猫もその特性を引き継いでいるため、ゴクゴク飲む!ということないです。
(むしろ、『猫がたくさん水を飲んでいる』というときは、病気である場合が多いです。)
無理に飲ませるとストレスになってしまうため、愛猫に水を飲んでほしい!という場合には、以下の記事をご参照ください。▼



③体重管理
太っていることが猫の尿道閉塞に関係している場合もあります。
食事の量を減らす、ダイエットフードにするなどして、適正体重を維持できるようにしましょう。
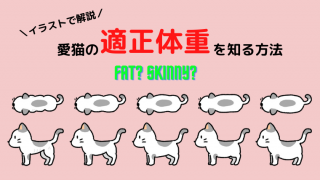
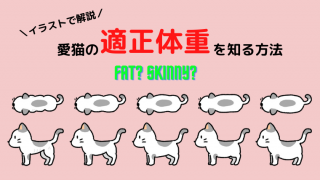
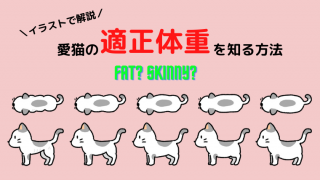
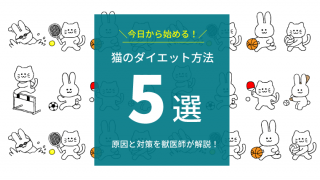
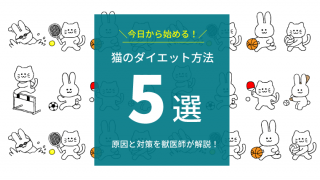
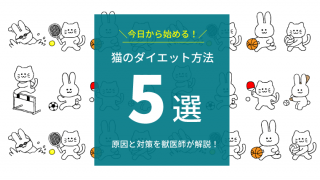
繰り返す猫の尿道閉塞には『会陰尿道造瘻術(えいんにょうどうぞうろうじゅつ)』


通常は、カテーテルによる解除により、よくなる(治る)ことがほとんどです。
手術が適応となる場合は、
- なんども尿道閉塞になる
- 尿道がせまい
- 尿道が損傷
- カテーテルで解除できない
などがあります。
会陰尿道造瘻術(えいんにょうどうぞうろうじゅつ)は、尿道を短くするオス猫のための手術です。
術後は感染症になりやすいため、陰部をきれいに保つ必要があります。
猫の尿道閉塞は、定期的な尿検査で予防


猫の尿道閉塞は、『尿検査をもとにした適切な食事管理+飲水』で予防をすることが可能です。
尿道閉塞になったことのある猫は、尿の状態を変えないと、再び閉塞してしまうリスクが非常に高いため、よりきちんと対策が必要です。
自宅での尿の取り方は、こちらを参考にしてください。▼



水を飲ませる方法は上記でもお伝えしましたが、ウェットフードをあげることです。
ウェットフードは、成分の60~80%程度が水分であり、嗜好性もよいため、食べるだけで水の摂取が可能です。
【まとめ】要注意!猫の尿道閉塞(尿閉)は急になる【症状や治療法をお伝え】
猫の尿道閉塞は、飲水量の減る冬場に、主にオス猫がなる緊急疾患です。
『愛猫がなんどもトイレに行くけど出ない』といった症状がある場合には、経過を見ず、すぐに動物病院に行きましょう。
猫の尿道閉塞は、定期的な尿検査、適切な食事と飲水で予防をすることができます。
ぜひ、尿検査を受けてみましょう!